ろうきん回想録
1950(昭和25)年に誕生したろうきんは、戦後復興の最中、金融機関からの借入れが難しかった労働者層へ積極的に融資し、はたらく人々の生活を守るうえで大きな役割を果たしました。以来70年近く、「はたらく仲間のための金融機関」として、夢と共感を創造し続けてきました。
-
Story
戦後復興の途上、自ら資金を出し合い
「はたらく仲間のための金融機関」をつくった敗戦から数年後、日本はいまだ混乱から脱しておらず、人々は先の見えない不安定な暮らしを送っていました。経済復興が急がれるなか、金融機関の資金は国や企業に回され、労働者への貸付は一向に行われません。その日の糧にも事欠く人々は、足りない生活費を工面するために質屋や高利貸しを頼るしかありませんでした。利息の支払いや取立てに追われ、生活は苦しくなるばかり。そうした状況を打開し、経済的に自立するために、「はたらく仲間の生活を救おう」と立ち上がったのは、他でもない労働者自身でした。
「自分たちのお金を自分たちのために使う。そんな自分たちのための銀行をつくろう。」
そうした声のもと、1950(昭和25)年、労働組合や生活協同組合が中心となって資金を集め、営利を目的としない日本で初めての福祉金融機関「労働金庫〈ろうきん〉」が誕生しました。企業や国のためではなく、はたらく仲間のための金融機関=ろうきんの歴史の幕開けでした。岡山県・兵庫県を皮切りに、その後、全国各地にろうきんが誕生していきました。大阪府では1952(昭和27)年、京都府・和歌山県では1953(昭和28)年、奈良県・滋賀県では1955(昭和30)年と、近畿の各府県でも次々とろうきんが産声をあげました。

開業当時の兵庫ろうきんの店舗 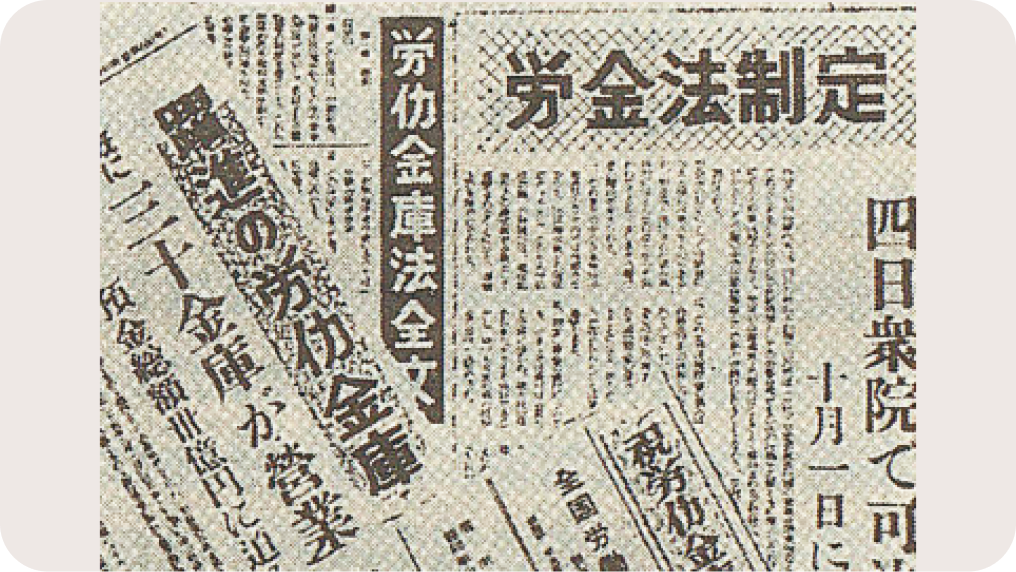
労働金庫法成立を知らせる新聞記事(出典:全国労働金庫協会五十年史) -
Story
人生を豊かに過ごすために
「貯蓄」を後押しする仕組みをつくる時代は高度経済成長期、企業に勤める人が急増した1960年代から、経済成長と足並みを揃えるように少しずつ賃金も増えていきましたが、まだまだ貯蓄する余裕のある人は多くありませんでした。
そのなかでろうきんは、はたらく人々の財産づくりを後押しするため、勤労者財産形成促進法(財形法)の制定に尽力し、「財形貯蓄(一般財形貯蓄)」が誕生しました。財形貯蓄とは、事業主が給料から天引きしたお金を積み立てる仕組み。1972(昭和47)年、全国のろうきんで財形貯蓄「虹の預金」の取扱いがスタートしました。
最初は「一般財形」のみでしたが、その後、定年退職後の生活を支えるための「財形年金」、マイホームの資金づくりに活かせる「財形住宅」も加わって、3種類になりました。
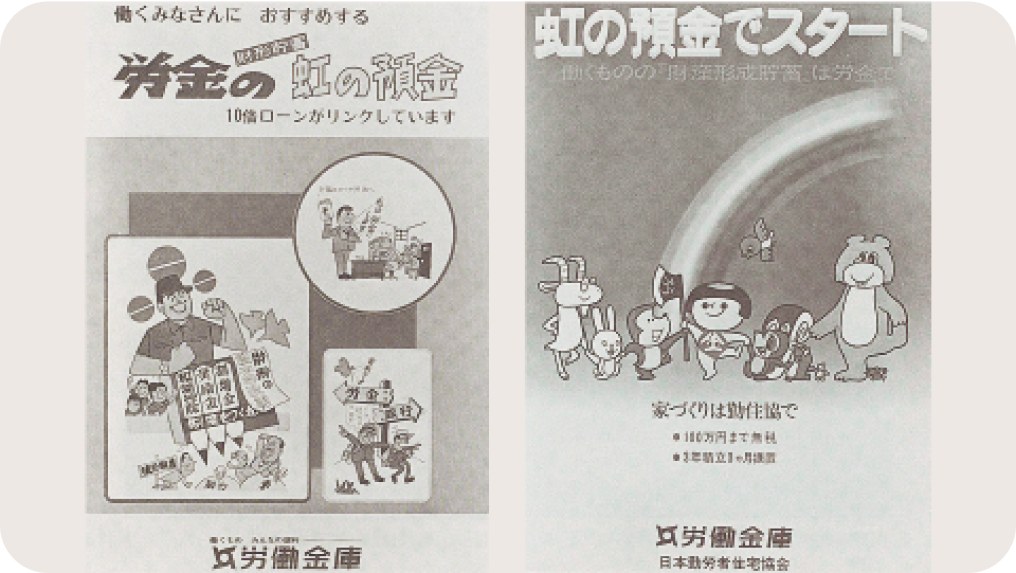
財形貯蓄「虹の預金」 ポスター(出典:全国労働金庫協会三十年史) 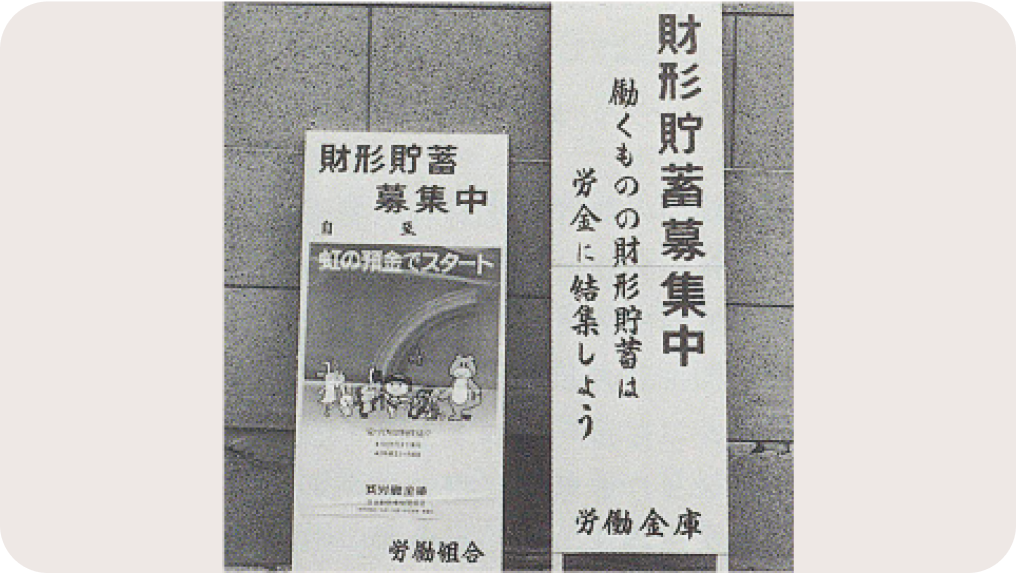
労働組合とともに、看板を設置して募集を呼びかける -
Story
マイホーム、マイカー、子どもの教育、
はたらく仲間とその家族の夢を応援するろうきんは、いつの時代も時流を捉え、はたらく仲間とその家族の豊かな暮らしを一番に考え、応援してきました。マイホームの夢を実現してきた住宅ローンはもちろんのこと、進学率の高まりに応じて、1978(昭和53)年には教育ローンの取扱いを開始。さらにマイカー時代の到来に呼応し、1986(昭和61)年には低金利の自動車ローンを発売しました。
その頃、社会はカードの時代へと突入。いつでも、どこでも、自由に借りられるカードローンが急増しました。しかし借りやすさの一方で、利息制限法と出資法の金利制限の間のグレーゾーンを利用した高金利に苦しむ人が増えていきました。それに歯止めをかけるべく、ろうきんは1986(昭和61)年、より手軽で低金利、かつ安全な新カードローン「マイプラン」を発売しました。
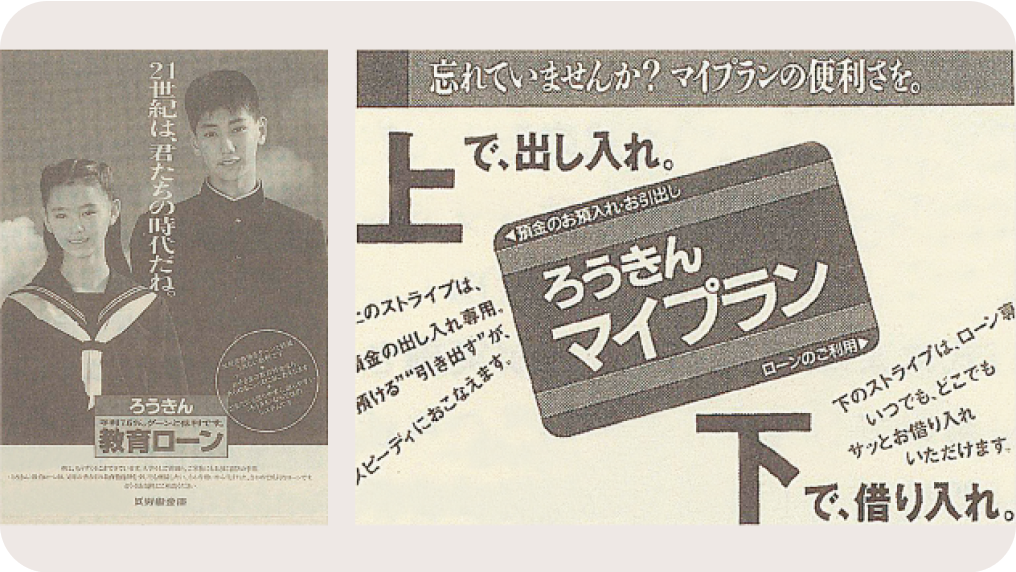
展開された「教育ローン」や「マイプラン」のキャンペーン(出典:全国労働金庫協会五十年史) 
ライフプラン相談会の開催 -
Story
苦しむ多重債務者を救いたい、
ろうきんの役割が認知される1980年代前半、「サラ金」と呼ばれる消費者金融による高金利の融資や厳しい取立てが増えていました。こうしたサラ金被害を食い止めるべく、1983(昭和58)年、全国のろうきんで「サラ金対策キャンペーン」を展開しました。この取組みが世論を喚起し、サラ金が社会問題化。新たな被害を防ぐとともに、サラ金被害者の救済活動が大きく前進しました。この動きにより、営利を目的としない福祉金融機関としてのろうきんの役割と存在理由が、社会にあらためて認知されることになりました。
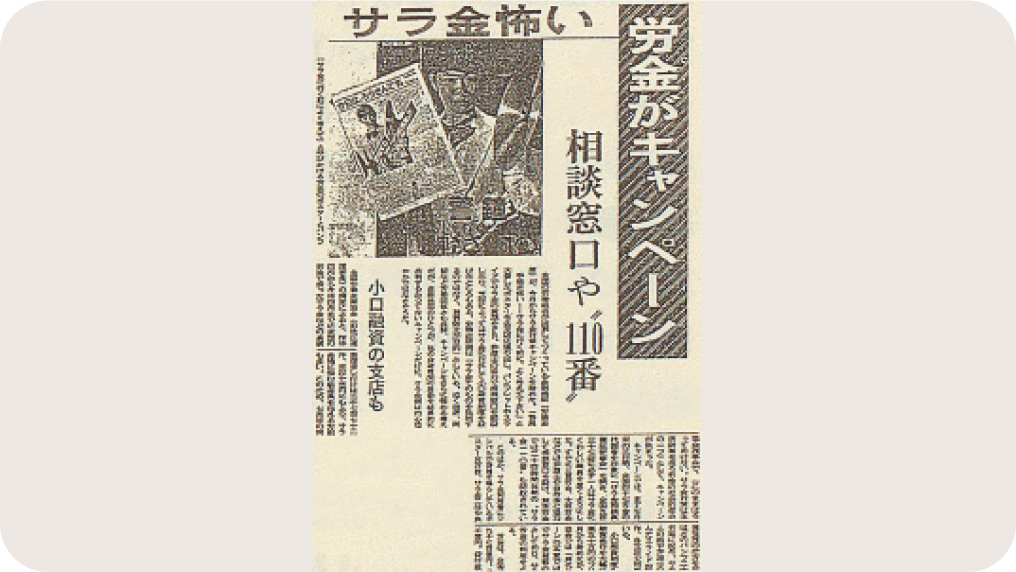
サラ金対策キャンペーンの新聞記事(朝日新聞、1983年2月19日付) 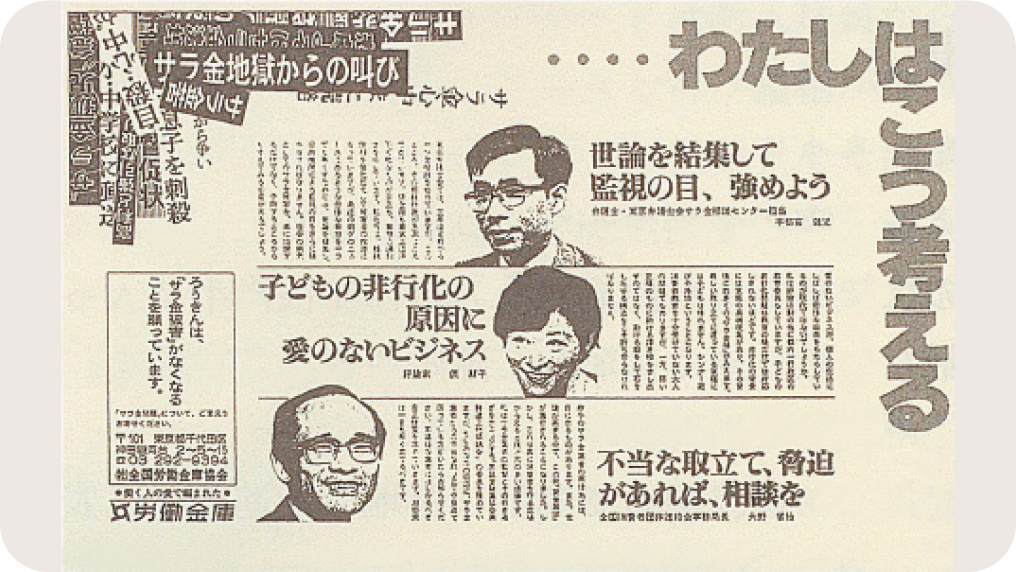
サラ金対策キャンペーンの新聞広告(朝日新聞、1983年8月29日付) -
Story
震災遺児支援定期「応援(エール)30」の取組み
会員と共に子どもたちの未来を支える1995年1月に発生した阪神・淡路大震災では、数多くの子どもたちが家族を失い、生活や学びの場を奪われました。被災地で多くの震災遺児が支援を必要とする中、〈ろうきん〉では、預金を通じて支援する震災遺児支援定期「応援(エール)30」を創設しました。その内容は、個人や団体の定期預金の利息の一部と〈ろうきん〉からの拠出を原資に、震災遺児への支援を行うものでした。以前より社会貢献預金と呼ばれるものはありましたが、この「応援(エール)30」は全国で大きな反響を呼びました。
会員に「応援(エール)30」の取組みの要請を行うと、「いつ来るかと待っていた。とってもいいことだよ。ろうきんに協力するよ」「夏のキャンペーンには、組織としてキッチリ取り組む。まかせておけ。」など、多くの会員から心強い賛同を得て、全国の〈ろうきん〉でその取組みが展開されました。
最終的に500億円近く預金が集まり、寄付総額は、2億3千万円以上にのぼりました。その寄付金は、奨学金や生活支援、文化活動など、さまざまな形で子どもたちの未来を支えました。

「震災遺児支援定期 エール30」リーフレット(一部抜粋) 
「震災遺児支援定期 エール30」取組み結果
(出典:月刊ろうきん1995年11月号)
